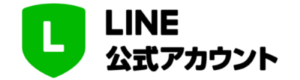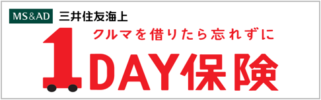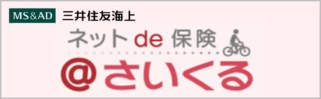先月の終わり頃から急に寒さが増しておりますが、体調はお変わりないですか。
どうか温かくしてお過ごしください。
ーーーーー
今回は、今月23日の“勤労感謝の日”についてご紹介いたします。
勤労感謝の日とは
「広く働く人々の勤労に向けて、感謝を示す日のこと。」
祝日として制定されたのは、1948年のことです。国民の祝日に関する法律の条文には「勤労をたっとび、生産を祝い国民がたがいに感謝しあう日」とあります。この条文が示す通り、勤労感謝の日とは、働くことや、仕事そのものを大切な習慣として重んじ、広く働く人々の勤労に向けて、国民同士が互いに感謝を示し合う日として制定した祝日です。
また、平成時代は天皇誕生日が12月23日にあったので、その日が1年で最後の祝日でしたが、令和になり、年内最後の祝日は、11月23日の勤労感謝の日となりました。

由来
「新嘗祭(にいなめさい)という祭祀に由来します。」
「新」は新穀、「嘗」は奉る、舌の上にのせて味をためすという意味で、「新嘗」はその年に収穫された新穀を神に奉って恵みに感謝し、口に感謝することを表しています。現在でも、新嘗祭は宮中をはじめ全国の神社で行われており、五穀豊穣を祈願する祈年祭と相対する重要な祭祀とされています。
この新嘗祭が勤労感謝の日となったのは、戦後のGHQの占領政策により、1948年に改められました。
なぜ11月23日?
「日付が11月23日になった理由は、新暦の導入にあります。」
由来となる新嘗祭は、旧暦では11月の第2卯の日に行われていました。1873年に、太陽暦(グレゴリウス暦)が導入された際、旧暦11月の第2卯の日を新暦にあてはめると、翌年の1月になってしまうため、新暦の11月第2卯の日である、11月23日となりました。翌1874年からは日付が変動しないよう11月23日で固定され、現在に至ります。